室内でも野菜が育つって聞いたのに、なかなか芽が出ない…
もしかしたらその原因、「光」にあるかもしれません。
完全室内・LEDライトでの栽培は、日当たりの悪い家や虫が苦手な方にとっては理想的な方法です。
でも、実は「種が光を好むかどうか」を知らずに種まきをしてしまうと、芽が出にくかったり、全く発芽しないこともあるみたいなんですよね。
この記事では、初心者の方にもわかりやすく、「好光性」「嫌光性」といった種の性質と、室内栽培での正しい種まきのコツを解説します。
好光性?嫌光性?まずは種の性質を知ろう
植物の種は、光に対する反応の違いによって大きく3つのタイプに分けられます。
▶ 好光性(こうこうせい)種子
発芽のときに光が必要なタイプ。
光が当たることで芽が出やすくなるため、土は薄くかけるか、むしろかけない方が良い場合もあります。
- レタス
- バジル
- シソ(しその種は特に強い好光性)
好光性の種は、発芽に光が必要なため、LEDライトの光をしっかり当ててあげることが成功のカギ。
特に、照度(ルクス)が足りないと発芽が遅れたり徒長の原因になります。
▶ 嫌光性(けんこうせい)種子
発芽には光を避けた方がいいタイプ。
しっかりと土や培地で覆って、暗くしておくことが重要です。
- ミニトマト
- 大根
- きゅうり
▶ 中間性種子(どちらでもOK)
明るくても暗くても発芽するタイプ
- スナップエンドウ
- ホウレンソウ
- 水菜
室内栽培ではなぜこの違いが大事なの?

「種をまけばそのうち芽が出るでしょ」と思いがちですが、光の有無は発芽率に大きく関わります。
特にLEDライトを使った室内栽培では、日光のように自然に変化する明暗がないため、種の性質に合わせた工夫が必要です。
- 好光性の種を深く埋めてしまうと、光が届かず発芽しません。
- 嫌光性の種を土に埋めずに光の下に置くと、光がストレスとなって発芽しにくくなります。
この違いを知らずに種まきをすると、「芽が出ない」「発芽がすごく遅れる」「発芽率が下がる」など、スタートからつまずくことになります。
【一覧】室内栽培でよく使う野菜と種の性質

好光性タイプ
レタス、バジル、シソ、ルッコラ、クレソン、小松菜、チンゲンサイ、カブ、、イチゴ、キャベツ、ブロッコリー、ニンジン、ごぼう、セロリ、春菊、ミツバ、白菜、水菜、パセリなど
嫌光性タイプ
ミニトマト、トマト、キュウリ、ラディッシュ(はつか大根)、オクラ、ピーマン、トウガラシ、なす、大根、にら、ネギ、カボチャ、タマネギ、メロン、スイカ、ゴーヤなど
中間性タイプ
スナップエンドウ、インゲンマメ、ソラマメ、ホウレンソウ、トウモロコシなど
私が今まで育てたものや、育ててみたいなと思ったものなど、種の性質が気になって調べてみたものを一覧にしてみました。
豆類は、どっちでも良いものが多いみたいでした。
トウモロコシは室内で栽培はしないかもですが、中間性のようです。
たまに、好光性〜中間、中間〜嫌光性となっていたり、本やネットの記事でも意見が正反対だったりもしていて、迷ってしまいます。
私は基本的には、光を嫌うタイプだけ、室内栽培では気にして遮光すれば良いのかなと思っています。
見分け方がわからないときはどうすればいい?

リストにも無かったり、ネットで調べてもわからない場合は、種の袋をよく見てみるとヒントがあるようです。
「好光性種子」は「覆土はごく薄く」「土はかけないで」などと書かれていることが多いです。
ただ、すべての種に明記されているわけではありません。
もし迷ったときは次の方法を参考にしてみてくださいね。
■ 基本の目安
- 種が小さい(米粒より小さい)=好光性の可能性大 → 覆土はごく薄く
- 種が大きめ =嫌光性の可能性大 → しっかり覆土するか、遮光する
■ 少量だけ実験してみる
育てたい種を少量だけ「光を遮らないそのまま」と「光を遮る」の両方で育ててみて、発芽の反応を比べてみるのもおすすめです。
私は、育てたい野菜が○○科の野菜か調べて、それと同じグループと同じでやってみたりしました。
LEDライトでの発芽を成功させる室内栽培のコツ

完全室内で育てる場合、太陽光の代わりにLEDライトを使用します。
でも、LEDライトは常に明るいので、嫌光性の種にはストレスになります。
▶ 好光性タイプの種まき
- スポンジ培地は上にばら撒くか、切れ目を入れても表面ギリギリに埋める
- バーミキュライトやハイドロボール培地は、上に少しかぶせるだけ。または、そのまま。
- 種まき後すぐにライトON(照度3000〜5000ルクス目安)
- 水切れ・乾燥防止のため霧吹きで表面を軽く湿らせる
(私は、そのあとに軽くラップをかけています)
▶ 嫌光性タイプの種まき
- スポンジ培地は、1cm程度切れ込みを入れて埋める
- バーミキュライトやハイドロボール培地は、しっかり覆土(1cm程度)
- 種まき後すぐにアルミホイルや黒い布などで遮光する
- 発芽したらすぐライトONに切り替える
※遮光期間の目安は1〜3日程度(発芽の兆しが見えたら終了)
発芽した後も、光の量が足りないと「ヒョロヒョロ」とした苗になってしまいます。
これは「徒長」と呼ばれる現象で、室内栽培では特に起こりやすいトラブルのひとつです。
まとめ:種のタイプを知るだけで、発芽がスムーズに!

初心者にとって、最初のハードルは「芽が出ないこと」。
でも、種の性質=「光が好きか嫌いか」を知っていれば、室内でもしっかり育ち始めてくれます。
- 「好光性」「嫌光性」は発芽に関わる大切な性質
- 室内栽培では、LEDライトの光の調整がカギ
- 種袋の表示や種の大きさでおおよその見当がつく
- 正しく種まきできれば、発芽率がグッと上がる!
『室内栽培って実際どうなの?』と気になる方には ▶︎ 初心者でも失敗しない!室内栽培を始める前に知っておくべきメリットとデメリット も参考になりますよ。
栽培はスタートが大事です。
種の特徴を知って、スムーズに育て始めましょう!
発芽から失敗を防ぐための関連記事


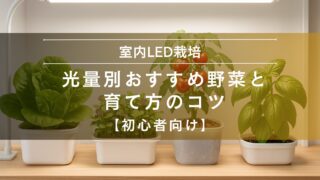




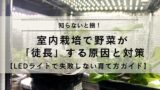


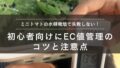
コメント